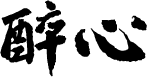2025年11月17日
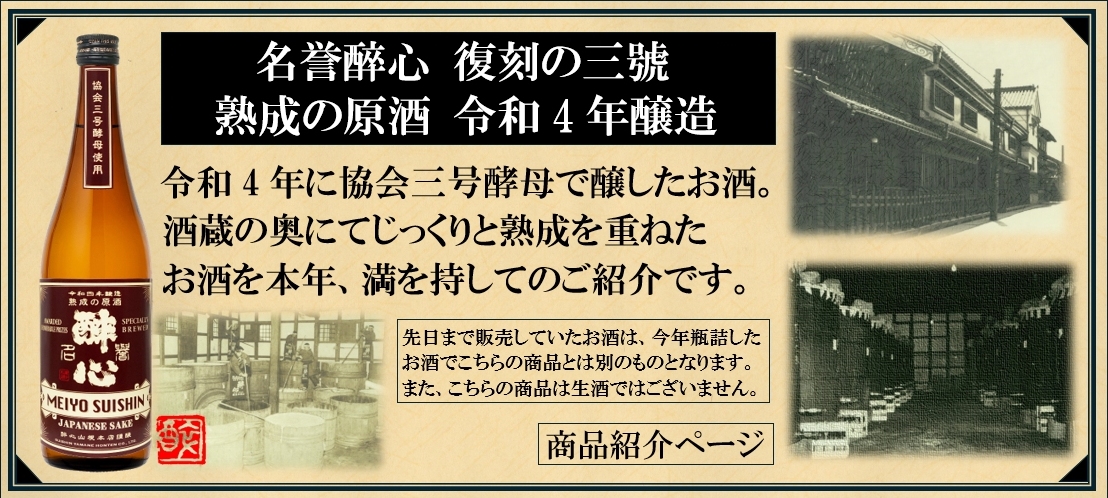
「名誉醉心 復刻の三號 熟成の原酒」
醉心は、大正8・10・13年の全国酒類品評会で3回連続して「優等賞」を受賞するという快挙をあげ、同13年(1924年)に「名誉賞」を授与、これを記念して高級酒ブランドとしての「名誉醉心」を創出しました。この時期、醉心のお酒は当蔵の蔵付き酵母「協会三号酵母」により育まれていました。
令和4年春、その「協会三号酵母」を使って醸し、令和7年11月に満を持しての発売となる「名誉醉心 復刻の三號 熟成の原酒」。広島県産米「中生新千本」と醉心自慢の超軟水をあわせたその風味は、3年数ヶ月に及ぶ熟成も相まって、芳醇そのものと相成りました。ここに、このお酒の発売を迎えるまでの経緯をご紹介致します。
時は平成22年(2010年)。この年、醉心は創業150年を迎えました。そこで、このおめでたい歳の記念となるようなお酒を造りたいと考えたのです。記念のお酒造りには、ぜひ「協会三号酵母」を使いたいと考えました。しかし、どんなコンセプトのお酒を造るのか、なかなか考えがまとまりませんでした。そんなある日の夕食の時、手に持ったご飯茶碗にふと目を落とし、自分たちが普段食べているお米、つまり地元産の食用米を「協会三号酵母」で醸したらどんなお酒が生れるだろう?はるか以前には、そうしたお酒造りが普通に為されていたのではないか?それを再現してみよう。そう思い至ったのです。
こうして、創業150年を記念する一つのお酒の概要がまとまりました。
使うお米は地元・三原市産の食用米。手に入れたお米は「ヒノヒカリ」でした。また、磨きは65%。かつて水車を使って精米をしていた頃に想いを致し、おそらくこのあたりが限度であったのだろうと想像したのです。
酵母は当然「協会三号酵母」。
そして水は、広島県中央部に聳える鷹ノ巣山の麓の井戸で汲み上げた超軟水。
「ヒノヒカリ」は適度な粘りがあり、食べ応えのあるおいしいお米と聞きます。普段から口にしているであろうこのお米でお酒を造ると、果たしてどの様な風味が生れるのか。満を持して出来上がったお酒は、白ワイン様とも、またマスカット様とも表現される特徴的な香りあるものでした。720ml瓶で僅か千数百本でしたが「創業150年記念 復刻の酒」として発売、好評を博し、あっという間に売り切れてしまいました。
三原の市街より瀬戸内海に注ぐ沼田川を遡ると、その水源である鷹ノ巣山に辿り着きます。そう、沼田川は、現在、醉心が使っている超軟水の井戸がある鷹ノ巣山より発しているのであります。
中世、沼田川の流域に「沼田庄」と呼ばれる荘園があったと聞きます。今でも沼田川の流域には多くの田圃が広がっていますが、これは幾世代にもわたる先人たちの営みが積み重ねられた姿なのかもしれません。
古来、酒の産地として成り立つには、近郊に米の産地があること、良い水が豊富に手に入ること、そして販路を得るために水運に恵まれていることが必要であると聞いたことがあります。上記のように、古くから三原の近郊には豊かな米の産地があったと考えられます。三原の街には沼田川を始めとする複数の川が注いでいることから、古来、水も豊富であったと類推することが出来ます。また、嘗ての小早川水軍の存在から、水運にも恵まれていたであろうと考えられるのです。
現在の三原市のかなりの部分はかつての令制国・備後に含まれますが、実際、備後三原は古くからお酒の産地として知られ、元和4年(1618年)、鞆に寄港した平戸の英国商館長リチャード・コックスが小舟を三原に送って、お酒を購入したとの記録があるそうです。また、江戸時代初期の広島城主であった福島家、そしてその後に城主となった浅野家からの徳川将軍家への献上品の一つとして三原酒が使われていたと言います。そして、正徳2年(1712年)に編纂された「和漢三才図会」で、備後三原は天下五指の銘醸地として紹介されていました。
醉心の創業は万延元年(1860年)。この年、醉心の初代当主である山根源四郎が備後三原にあった酒蔵「出羽屋」を購入したことからその歴史は始まります。従って、酒蔵自体はそれ以前から存在していたのです。家が代わったことから、創業以前の歴史は詳らかではありません。しかし、醉心の本店が所在する一帯は、16世紀後半に築城された三原城の城下町として早くから整備されたと聞くので、上記のように備後三原が銘醸地として知られていた頃には、既にここに酒蔵があったのかもしれません。もし、そうであるなら、その頃のお酒は、おそらく三原近郊で収穫されたお米で醸されていたのでしょう。さらに想像を膨らませるなら、先に記した「創業150年記念 復刻の酒」のようなお酒であったのかもしれません。
令和4年の春先、再び「協会三号酵母」を使って一つのお酒を醸しました。これは、令和6年に迎える「名誉賞受賞100年」を念頭とする試行錯誤の中でのことでありました。この頃の数年間、先の「創業150年」での酒造りを参考に、多様なお米による「協会三号酵母」の酒造りを模索していたのでありました。
令和4年に使ったお米は、広島県産の「中生新千本」です。嘗て、食用米として広島県内で広く栽培されていたお米であり、程よい甘味と粘りがあり、炊いたそのままを食べておいしいとのことでした。また、酒造りに使われることも多く、醉心の酒造りでは純米酒などに使用され、スッキリとした特徴的な風味のお酒を育んでいます。
そのお米を、「協会三号酵母」、そして鷹ノ巣山山麓の井戸で汲み上げた超軟水とあわせて醸したお酒は、スッキリした香りと品の良い酸味を感じさせる、透明感のある風味です。反面、このお酒にはまだ成長の余地がある、まだ味が膨らむ余地があるとも感じました。そこで、少なくともあと3年、蔵内でこのお酒を寝かせることにしたのです。その後、秋を迎える度、このお酒の試飲を繰り返すことと致しました。
そして、令和7年9月、上槽(お酒を搾ることです)より3年数ヶ月となり、また4度目の秋を迎えたこのお酒を試飲したところ、芳醇で、まさに飲み頃の風味に昇華しておりました。そこで、同年11月を期しての発売へと至った次第です。
上述の通り、様々な試行錯誤の中から生まれたお酒です。また、3年余りの熟成を経て整ったこの風味を再度にわたり育むことは容易ではないと存じます。あえて、このお酒の風味の詳細やおすすめの飲み方については、多くを語りません。二度とは現れぬであろう令和4年のこの風味を、ご自分に合う飲み方を探求しつつ、ぜひ、お楽しみください。